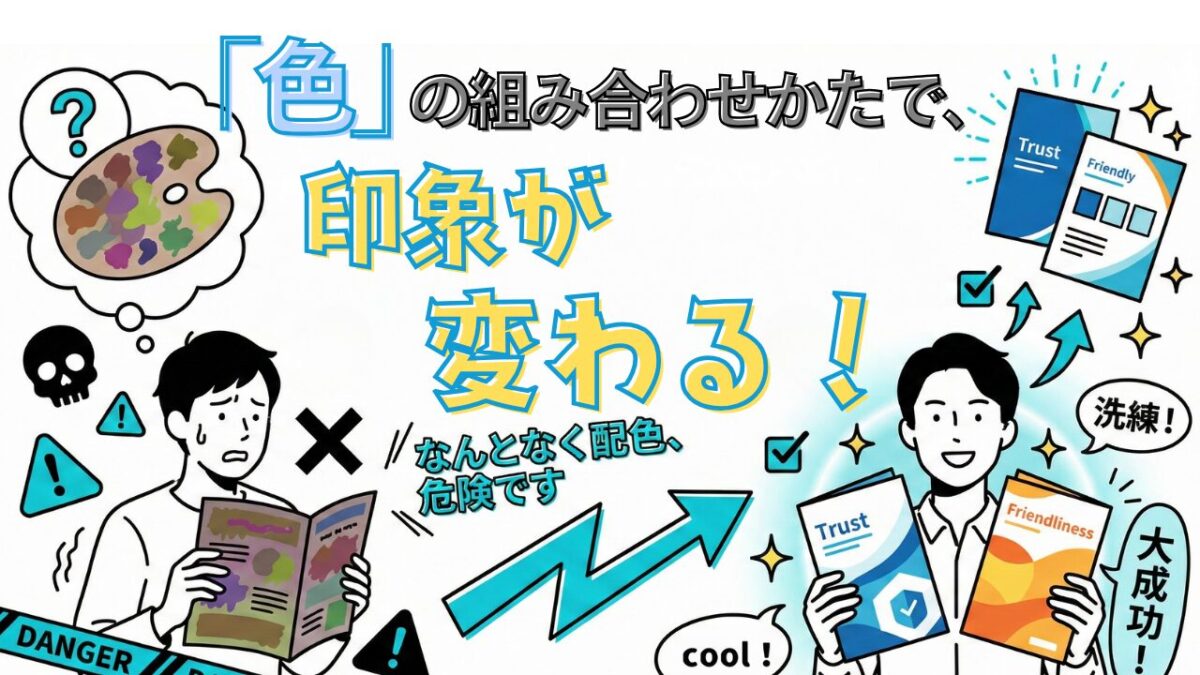
「色」の組み合わせで、印象は…
04
2
2026
point
制作のコツ
[コラム]

そんな経験、ありませんか?
パンフレット印刷は「データさえ同じなら毎回同じように仕上がる」と思われがちですが、実はそうとは限りません。
用紙や印刷方法、データ設定のちょっとした違いが、大きな差を生むことも。
このコラムでは、
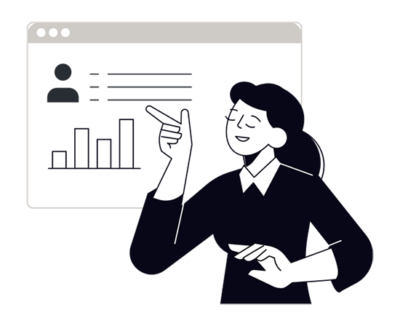
そんな方に向けて、印刷仕上がりの違いが起こる理由と、その“想定と対策”についてわかりやすく解説します。
知らないと困るけど、知っておけば安心。
後悔しないパンフレット印刷のための“基本のき”を、ここでまとめておきましょう。
目 次

パンフレットや販促物の制作に関わっている方であれば、こうした“思っていたのと違う”経験、一度はあるのではないでしょうか?
せっかく時間と費用をかけてつくったにもかかわらず、
手元に届いた印刷物を見てガッカリしてしまう――
これは非常にもったいないことです。
実は、印刷物の仕上がりは、デザインデータだけでなく、「紙」「インク」「機械」「環境条件」など、さまざまな“見えない要因”が複雑に関係しています。
それらを知らずに制作を進めてしまうと、期待した仕上がりにならないばかりか、企業の信頼感やブランドイメージを損ねるリスクすらあります。
これらを制作担当者の視点で、わかりやすく解説します。
貴社の「伝えたい」を、確実に「伝わる」かたちにするために。
読み終える頃には、印刷物への見え方がきっと変わるはずです。
パンフレットの制作を外注する際、多くの方がデザインや内容に意識を集中させがちですが、実は「印刷工程」そのものが、仕上がりの品質に大きく影響を与えています。
ここでは、「同じデータなのに仕上がりが違う…」という事態を防ぐために、印刷品質に差が出る主な原因を7つの視点から解説します。
印刷には大きく分けて、オフセット印刷とオンデマンド印刷の2種類があります。仕上がりに違いが出る代表的なポイントのひとつです。
版(はん)を作って印刷する伝統的な方法。
一度に大量に刷る場合にコストパフォーマンスが良く、色の再現性・安定性が高いのが特徴です。写真集や美術書、高級パンフレットなどに使われることが多く、色ムラが出にくく、グラデーションや細かなディテール表現にも強い印刷方式です。
ただし、版の作成にコストと時間がかかるため、少部数には不向きというデメリットもあります。
デジタルデータを直接印刷する方式。
版を作らずに印刷できるため、1部からの出力も可能で、小ロット・短納期の印刷に非常に便利です。試作品、店舗限定配布、イベント用、パーソナライズ印刷などに向いています。ただし、オフセットに比べると色の再現性や安定性にわずかな差が出ることも。特に、ベタ塗りの均一性やグラデーションの滑らかさで違いを感じやすい傾向があります。
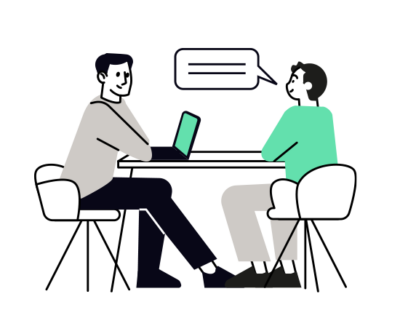
パンフレット印刷で「前回と仕上がりが違う」と感じた場合、印刷方式が変わっていなかったかをまず確認してみましょう。「どちらの方式で印刷したのか」も、発注時に明示・記録しておくことが大切です。
最近では、ネットから簡単に注文できる格安の印刷サービスも多く利用されています。
これらのサービスでは、印刷方式を自分で選べる場合もあれば、部数や仕様によって自動的に印刷方式が決まってしまう場合もあります。
特に少部数(100部以下など)の場合は、自動的にオンデマンド印刷になることが多く、前回がオフセット印刷だった場合、思わぬ仕上がりの差が出ることもあります。
・印刷方式は「自動選択」か「指定可能」か?
・少部数でもオフセット印刷ができるか?
・前回と同じ方式で印刷できるかどうか?
パンフレットの品質を安定させたい場合は、印刷会社ごとの仕様や対応範囲を事前に確認しておくことが重要です。
発注前に「どの印刷方式になりますか?」と確認するだけでも、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
「前回と同じマットコート紙で」と指定したのに、
なぜか今回のパンフレットは少しツヤ感が違う…?
――そんな経験はありませんか?
「マットコート紙」や「上質紙」といった用紙は、名前が同じでも、メーカーや製造ロット(生産の時期・単位)によって微妙な違いがあります。
たとえば:
などに差が出ることがあります。
紙の主原料である木材パルプは、農作物と同じく天然素材。
そのため、製造時期や原料の状態によって微細な個体差が生じるのです。
特に、写真やイラストの発色が重要なパンフレットでは、
このわずかな違いが「全体の印象」を大きく左右する要因になります。
用紙にはさまざまな表面仕上げがあります。
同じ種類の紙であっても、表面加工の差によってインクの乗り方や光の反射が変わり、見え方に影響を与えます。
意外と知られていませんが、使用している用紙が「輸入紙」か「国産紙」かによって、仕上がりの印象が微妙に変わることがあります。
特にネットの格安印刷会社では、コストを抑えるために輸入紙を標準使用しているケースが多く、こちらが意図しないまま輸入紙が使われていることも珍しくありません。
また、安価なプランでは国産紙を選ぶオプションがそもそも存在しない場合もあります。
とはいえ、最近ではネット印刷でも国産紙を指定できる会社も増えてきています。
仕上がりの質感や信頼性を重視したい場合は、以下を確認してみましょう。
・国産紙を取り扱っているか?
・輸入紙と国産紙が選べるか?
・輸入紙がデフォルトで使われていないか?
 国産紙は微妙な差ではあるものの、印刷後の色味や手触り、安定性において「やっぱり違う」と感じる声も多いのが実際です。特に企業の販促物など、「見た目の質感」がブランドイメージを左右するケースでは、国産紙を選べる環境を整えることが小さな差を生むポイントになります。
国産紙は微妙な差ではあるものの、印刷後の色味や手触り、安定性において「やっぱり違う」と感じる声も多いのが実際です。特に企業の販促物など、「見た目の質感」がブランドイメージを左右するケースでは、国産紙を選べる環境を整えることが小さな差を生むポイントになります。
「同じ印刷会社に頼んだのに、なぜか前回と雰囲気が違う…」
そんな違和感を覚えたことはありませんか?
実は、同じ会社・同じデータでも仕上がりに差が出ることがあります。
その理由のひとつが、使用する印刷機や担当オペレーターの違いです。
印刷工場の湿度や気温も仕上がりに関係します。
特に紙は湿気を吸いやすく、季節によって伸び縮みする繊細な素材です。
こうした微細な変化が、写真の精細さや色の鮮やかさ、仕上がり位置のズレなどに表れることがあります。
たとえば、ある機械は赤みが強く出やすかったり、別の機械では紙送りのクセでわずかにズレやすかったりする――といったこともあります。
一見すると気づかないほどのわずかな差ですが、ブランドの世界観や、商品の魅力を伝える販促物のような印刷物では、その“微差”が意外と大きな影響を持ちます。
前回と同じ印刷会社でも、「同一機械・同一条件で」印刷されるとは限りません。品質を重視する場合は、事前に「本機校正(実際の印刷機での確認)」を依頼する必要があります。
納期に余裕があれば、印刷前に環境(湿度・季節)も考慮したスケジューリングを検討するとベターです。
実は、印刷物の“色合わせ”は非常に繊細な作業であり、本当の意味で「前回と同じ仕上がり」を再現するためには、色校正(試し刷り)だけでは不十分なこともあります。
もっとも確実なのは、実際の印刷時に現場へ立ち会い、印刷機を回しながらオペレーターと一緒に色を合わせていく方法です。
見本(前回の印刷物)を横に置いて直接比較・指示ができる点がポイントです。
この「立ち会い印刷」によって、イメージとのずれを最小限に抑えることができます。
しかし、ネットの格安印刷では対応できないケースがほとんどです。
こうした対応はすべての印刷会社で可能なわけではありません。
 特にネット経由の格安印刷サービスでは、作業工程が自動化されており、立ち会いに非対応。人的コスト削減のため、細かな調整ができません。
特にネット経由の格安印刷サービスでは、作業工程が自動化されており、立ち会いに非対応。人的コスト削減のため、細かな調整ができません。
印刷の立会が必要な場合は、事前に「立ち会い印刷」は可能か?前回印刷時の色見本を持参しての色合わせに対応してもらえるか?印刷オペレーターとの色調整ができる体制があるか?について確認しておきましょう。
印刷物のクオリティにこだわりたいときは、「どこまで対応してもらえるか」も含めて印刷会社を選ぶことが大切です。
印刷が終わったからといって、パンフレットの制作は“完成”ではありません。
実は、印刷後の「加工・仕上げ」こそが、最終的なクオリティを大きく左右する要素です。
たとえば、以下のような加工は、色味の見え方や全体の印象、手触り、耐久性に影響を与えます:
これらは“目立たないようで、完成品の印象に直結する”工程です。
意外と見落としがちですが、前回と加工内容や仕上げの方法が少しでも異なると、印象がガラッと変わってしまうことがあります。発注時には以下の点を必ず確認しましょう:
加工・仕上げは単なる“おまけ”ではなく、パンフレットの「完成度」を左右する最後の大事なステップです。
印刷だけでなく、仕上げまで含めて全体の設計図を描くことが、プロ品質への近道です。
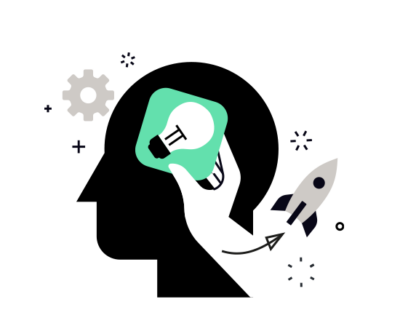
濃い色(黒・紺・赤など)のベタ塗りを表紙や裏表紙に使っているデザインでは、折り目の部分が白くはげたように見えることがあります。特に厚紙を使用した場合に目立ちやすく、どんなに美しいデザインでも、この「折れ割れ」で一気に安っぽく見えてしまうことも。
これを回避するためにも、厚紙+濃い色ベタには「スジ押し加工」を追加しましょう。
「スジ押し加工」とは、あらかじめ折る位置に筋を入れておく処理のこと。
これを加えることで、紙割れを防ぎ、見た目も美しく保つことができます。
白や薄い色のデザインなら、割れが目立たないため、スジ押しなしでも大きな問題はありません。
とはいえ、気になる場合は相談を。
折り加工も、仕上がりの品質に直結する大切な要素です。
用紙やデザインに応じて、加工の有無を必ず確認しましょう。
「前回は色校正をしたけど、今回は時間がないからスキップで」
そんな判断が、思わぬ仕上がりの差につながることがあります。

色校正とは、本番と同じ用紙・印刷方式で印刷し、色味や仕上がりを確認する工程のこと。
これを行わずに印刷すると、実際の色や濃さ、細かい部分の違いに気づけないまま、大量印刷に進んでしまう可能性があります。
特に以下のケースでは色校正を強く推奨します:
時間やコストの都合で省略されがちですが、仕上がりに納得できるかどうかを左右する重要な確認プロセスです。
迷ったときほど、「色校正をする」ことが安心につながります。
印刷の仕上がりを左右する最後の大きな要因が、「どの印刷会社に、誰に頼むか」です。
同じ会社でも、担当者が変われば、これまでの微調整の履歴や感覚が引き継がれないことも。
特に外注先を変更した場合は、色や用紙、加工に関する細かな意図が伝わりきらず、仕上がりに差が出る可能性があります

「とにかく安く早く」と価格だけで選ぶと、ヒアリング不足・確認不足によるトラブルが発生しやすくなります。
信頼できる印刷会社とは、こちらの意図を正しく理解し、要望に合わせた提案や注意喚起ができ、過去の履歴もふまえて、品質を安定させてくれる。
――そんな「制作パートナー」であるべきです。
印刷は“仕様書通り”だけではカバーできない繊細な工程です。
だからこそ、信頼できる担当者と継続的にやり取りを続けることが、何よりの安定につながります。
印刷物の品質は、実は納品されるまでの“扱い方”でも差が出ます。
以下のような「梱包のきめ細やかさ」も、見落とせないポイントです。
ネットの格安印刷では、梱包スタイルを選べない場合がほとんどですが、中には有料オプションで梱包方法を選べる会社もあるので、事前にチェックしておくと安心です。
濃いベタ面のあるパンフレットでは、重ねた際の「色移り」リスクがあります。
一部の印刷会社では、納品時に間に合紙(あいし)を挟んでくれることも。
ただし、こうした細やかな配慮は、人手がかかるため、価格が高めになる傾向があります。
「予算」「目的」「納品形態」をふまえて、印刷会社選びの参考にしてみてください。
印刷仕様書は“品質の設計図”です。
細かい情報までしっかり記録し、次回発注時に印刷会社と共有しましょう。
「前回と同じ仕様で」と伝える際の、具体的な根拠になります。
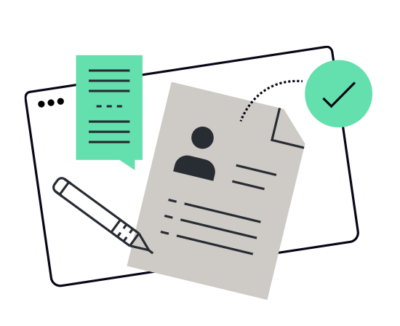 パンフレットの品質を安定させるためには、「いつ作ったものか」を明確にしておくことも大切です。
パンフレットの品質を安定させるためには、「いつ作ったものか」を明確にしておくことも大切です。
裏表紙などに小さく「印刷年月」を記載しておくと、再印刷時や社内での確認がスムーズになります。
また、仕上がった印刷物は、現物を必ずバックアップとして保管しておきましょう。
色味・紙質・加工など、次回の参考資料として非常に役立ちます。
ちょっとした工夫ですが、「前回と同じにしたい」というときの強い味方になります。
データはちょっとした違いでも、色味に影響が出ることがあります。
安易な再書き出しや、異なるソフトウェアでの編集は、思わぬ色の変化を引き起こす可能性があります。
仕上がりの色にこだわる場合、色校正は不可欠です。
オンデマンド印刷では簡易校正の依頼がしやすいので積極活用を。
印刷前に、社内プリンターで出力見本を確認することはよくありますが、その色味を信用してはいけません。
このように、「見るべきポイント」を明確に分けて確認することが、失敗のないパンフレットづくりにつながります。
可能であれば、前回と同じ印刷環境を依頼しましょう。
仕上がりの安定には、「会社」よりも「人」と「機械」の継続性が鍵になります。
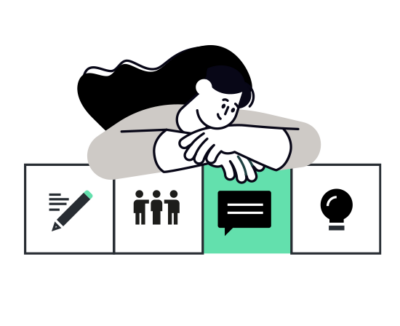
ここまで、印刷物の仕上がりに影響を与えるさまざまな要因と、「前回と同じ品質」を再現するための対策についてご紹介してきました。
改めて大切なのは、以下の3点です。
印刷は、機械的な作業に見えても多くの繊細な要素が絡み合う工程です。
色味や質感に違和感を感じた場合は、原因を整理し、次回にどう反映させるかが改善の第一歩になります。
デザインは「見た目」以上に、「伝える力」を持つもの。
販促物のデザインは、単に美しさを追求するだけでなく、貴社のメッセージを正確に届け、行動を促す重要なツールです。
そしてその力を最大限に引き出すには、印刷という最終工程まで、丁寧に設計することが欠かせません。

私たちは、制作のパートナーです。
当社では、「伝えたい」を「伝わる」に変えるお手伝いをしています。
デザインから印刷まで一貫してサポートし、効果的な販促物づくりをトータルでご提案しています。
「なんとなく印象が弱いパンフレットを見直したい」
「他社と差がつく表現をしたい」
「印刷まで任せて、確実にクオリティを保ちたい」
そんなときは、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社の目的・課題に応じた“納得できる一冊”を、プロの視点でご提案いたします。
![デザインゲット[株式会社ノーブランド]](https://www.design-get.com/img/logo-footer.png)
 0120-511-500
0120-511-5000120-511-500(月〜木9:00〜18:00:お問合せ番号9)
![デザインゲット[株式会社ノーブランド]](https://www.design-get.com/img/logo.png)
![テンプレプラス[株式会社ノーブランド]](/img/logo-m.png)