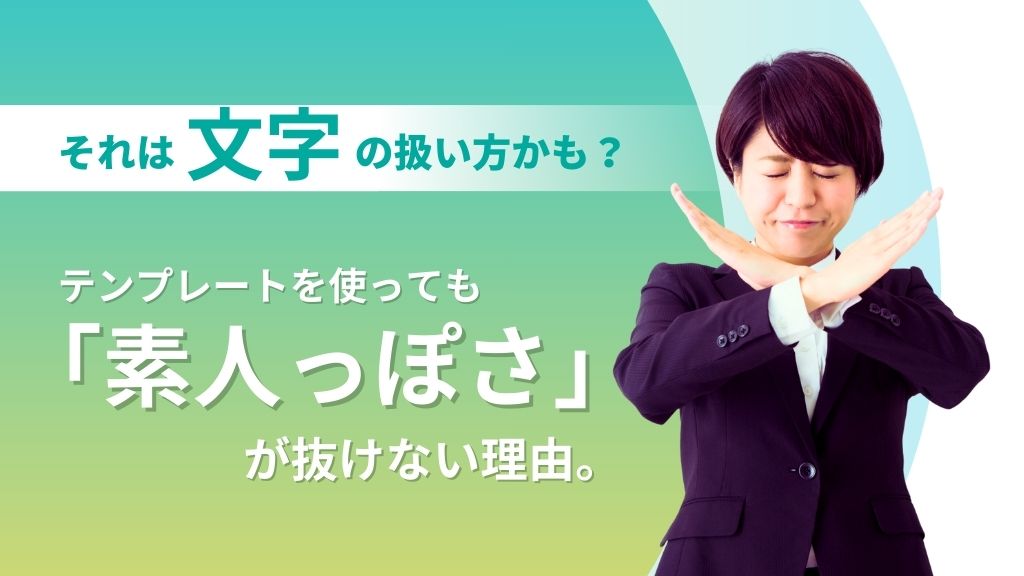
テンプレートを使っても「素人…
11
12
2025
point
制作のコツ
[コラム]
「パンフレットを作りたいけど、何を書けばいいのか分からない…」そんなお悩みに応えるために、会社案内パンフレットの中身の決め方を、構成の基本から具体的なコツまで丁寧に解説します。
ありがちなNG構成を避け、読者目線で伝わる内容にするには?
30年にわたって企業のパンフレット制作に携わってきたプロの視点で、“伝わる紙面”に変えるためのヒントを詰め込みました。
目 次
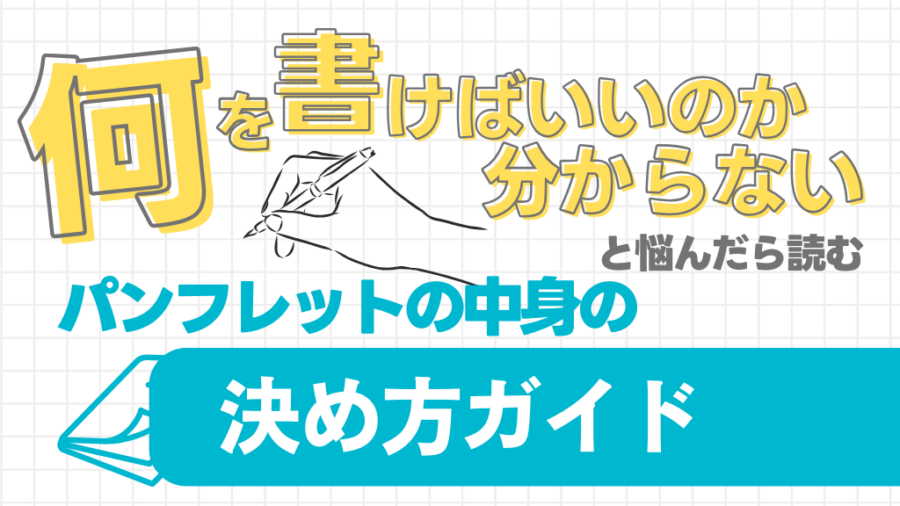

「パンフレットを作りたいけど、何を書けばいいのか分からない…」
実は、この悩みを抱える方はとても多いです。
上司から「会社案内を作ってほしい」と任されたものの、何から手を付ければいいのか分からない——
そんな戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。
ありがちなのが、「会社紹介だけで終わってしまう」パンフレット。
でも、本当に伝えるべきなのは、“自分たちのこと”よりも、「読んだ人に何を届けたいか」です。
そこで本記事では、30年にわたり企業のパンフレット制作を手がけてきた私たちの経験をもとに、
「迷わず進められる内容の決め方」をガイドとして記事をまとめました。
これを読めば、初めてのパンフレットづくりでも、伝わる内容構成のヒントが見つかります。
会社案内パンフレットでありがちな失敗例をまとめました。
「これ、うちのパンフかも…」とドキッとした方もいるかもしれません。
でも安心してください。
この記事を読み終える頃には、改善のヒントが見えてくるはずです。
 結果、「読んだ人の心に何も残らない」パンフレットになってしまうのです。
結果、「読んだ人の心に何も残らない」パンフレットになってしまうのです。
それでは、どのような目線で会社案内パンフレットを作っていけばいいでしょうか?
以下に解説していきます。
読者が本当に知りたいのは、
「で、この商品(サービス)は、私にどう役立つの?」という点です。
まずは、読者が抱えるお悩みをどんな形で解決できるのかを、徹底して「相手の視点」で考えてみましょう。
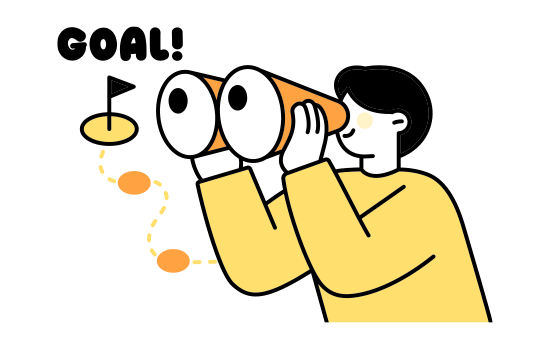 自分が困っている立場だったとして、
自分が困っている立場だったとして、これが最初のチェックポイントです。
解決策やメリットが具体的にイメージできなければ、興味や関心を持ってもらうことはできません。
まずは、自社の商品・サービスが読者にとってもたらす最大のメリットを整理し、それを中心に伝える構成を考えましょう。
 次に大切なのは、
次に大切なのは、
紹介する商品やサービスが、読者にとって“イメージしやすい”形で伝わっているかという点です。
専門用語や難解な言い回しばかりのパンフレットでは、読む気をなくしてしまいます。
初めてその商品に触れる人が見ても、ひと目で内容が理解できる紙面であることが大切です。
説明文を分かりやすくするのはもちろん、イメージを補う写真や具体的な事例、ビフォーアフターを掲載することで、読者は自分ごとのように捉えやすくなります。
結果として、「これは私にも関係がある」と感じてもらいやすくなるのです。
 会社案内パンフレットにおいて、最も重要なのは「信頼性」を得ることです。
会社案内パンフレットにおいて、最も重要なのは「信頼性」を得ることです。
どれだけ魅力的なサービスや商品でも、読み手に「ここは信用できる」と思ってもらえなければ、行動にはつながりません。
そのためには、まずデザインの整った印象や、わかりやすい説明文が欠かせません。
視覚的にすっきりと読みやすく、論理的に伝わる構成は、それだけで自然と信頼感を与えます。
さらに、以下のようなコンテンツを盛り込むことで、読者に「安心感」や「納得感」を与えることができます。
これらがあることで、「ちゃんとしていそう」「ここなら大丈夫そう」と思ってもらえるパンフレットになります。
すでにキャッチコピーをお持ちの企業であれば、表紙に大きく掲載するのがおすすめです。
キャッチコピーは短い言葉で企業の魅力や方向性を伝える、印象づけのための大切なエッセンス。
パンフレットの冒頭に添えることで、読者の関心を一気に引きつけることができます。
まだキャッチコピーがない場合は、この機会に考えてみるのもひとつの手です。
パンフレット制作は、自社の強みや想いを再確認するチャンスでもあります。
なお、最近は英語のフレーズを使うケースも見られますが、ターゲットが日本人であれば、できるだけ平易な日本語のほうが伝わりやすいでしょう。
どうしても英語を使いたい場合は、誰もが聞いたことのある、意味がイメージしやすい単語を選ぶのがポイントです。
良いキャッチコピーは、「読者に何かしらの“絵”を思い浮かばせるか」が大切です。
抽象的すぎる言葉や、どの会社にも当てはまりそうな定型句ではなく、自社らしさや対象ユーザーへの共感を込めることが成功のカギです。
会社案内パンフレットで忘れてはならないのが、「ベネフィット」の提示です。
「ベネフィット」とは、
つまり、読者が貴社の商品やサービスを使うことで、どんなメリットが得られるのかを、明確に伝える必要があります。
たとえば、以下のような表現です:
また、人は「得をすること」よりも、「不安が解消されること」に強く反応すると言われています。
そのため、場合によっては以下のような切り口が効果的です。
読者の不安や悩みにどう応えるか。
そこにこそ、自社ならではの「強み」を組み合わせることが、心を動かすパンフレットへの第一歩です。
「読者(顧客)が、その商品やサービスを利用することで得られる利益や価値」のことです。
単なる「特徴(スペック)」ではなく、その特徴が“相手にとってどう役立つのか”を伝えることがポイントです。
会社案内パンフレットでは、貴社の商品やサービスの概要をきちんと説明することが大切です。
単なる「こんなものを扱っています」という紹介にとどまらず、以下のような情報を丁寧に盛り込みましょう。
よくご相談いただくのが、「価格を載せるべきかどうか」というお悩みです。
「料金を載せたら“高い”と思われてしまうのでは…」
「将来的に価格改定したときに差し替えが面倒…」
こうした不安はごもっともです。
ですが、料金がまったく載っていないパンフレットは、読者にとって“判断材料がない”状態ともいえます。
すべてを細かく明記する必要はありません。
読者がサービスの価値をイメージしやすくなるよう、最低料金・平均価格帯・モデルケースなどの目安だけでも載せることをおすすめします。
たとえば、
「〇〇コース:月額5,500円〜」
「平均相場:初回◯万円〜 ※内容により変動します」
といった形で表現すれば、透明性が伝わり、信頼感アップにもつながります。
会社案内パンフレットにおいて、お客様の声や導入実績の掲載は、読者にとって大きな安心材料となります。
特に「実績の紹介」は、
「こんなに多くの人が使っているなら、きっと大丈夫」
という安心感を生み、読者の中にある「失敗したくない」という心理的ハードルを下げる効果があります。
お客様の声を信頼される形で掲載するために
一方で、「お客様の声」はその扱いに注意が必要です。
あまりに抽象的で曖昧なコメントは、
「これはサクラでは?」
と疑念を抱かれる原因にもなりかねません。
たとえば、
◯「納期が早く、想像以上に丁寧な仕上がりでした。◯◯業・40代・男性」
このように、具体的な内容+属性(年代・業種など)を添えることで、信ぴょう性は一気に高まります。
ありがちな「良かったです」だけの声は逆効果になる場合もあるため、要注意です。
どれだけ魅力的な内容を伝えても、読者が次に「どうすればいいか」が分からなければ、パンフレットの効果は半減してしまいます。
つまり、会社案内パンフレットには、読者がすぐに行動できる“導線”を明記することが不可欠です。
せっかく興味を持ってくれた読者が、「どう連絡すればいいか分からない」「アクセスしづらい」と感じてしまうのは大きな機会損失。
読者が迷わず次のアクションを起こせるように、わかりやすく・目につく場所に・複数の手段でコンタクト情報を載せましょう。
Q:商品が1つしかない場合でも、パンフレットは必要ですか?
会社案内パンフレットは、商品の“数”ではなく、その商品・サービスをどう伝えたいかに基づいて作るべきものです。
「たいした内容じゃないから不要かな…」と思うかもしれませんが、
その商品に自信や想いがあるなら、きちんと伝える工夫をすることが大切です。
むしろ、1つの商品しかないからこそ、
…といったストーリーや強みをしっかり伝えるパンフレットが、購入や信頼につながる武器になります。
Q:情報が多くなりすぎるのが心配です
限られた紙面の中で、「何を伝えるべきか」をしっかり吟味し、
読みやすく整理された構成にすることが大切です。
「あれもこれも載せなければ…」と詰め込みすぎると、かえって伝わりづらくなってしまいます。
という視点で情報を取捨選択していくと、メッセージがクリアになり、読者の理解も深まります。
Q:パンフレットに代表挨拶は入れたほうがいいですか?
とくに小規模事業者や地域密着型のビジネスでは、代表者の人柄や想いが伝わることで、安心感や親近感につながることがあります。
ただし、堅苦しい内容や抽象的な言葉ばかりにならないよう、「なぜこの事業をしているのか」「どんな想いでサービスを提供しているのか」を具体的に語るのがポイントです。
Q:ウェブサイトがあるので、パンフレットは不要では?
一方、ウェブサイトは検索・比較・詳細確認といった、あとから調べる場として機能します。
両者をうまく連携させることで、より強い信頼形成と行動導線が生まれます。
![デザインゲット[株式会社ノーブランド]](https://www.design-get.com/img/logo-footer.png)
 0120-511-500
0120-511-5000120-511-500(月〜木9:00〜18:00:お問合せ番号9)
![デザインゲット[株式会社ノーブランド]](https://www.design-get.com/img/logo.png)
![テンプレプラス[株式会社ノーブランド]](/img/logo-m.png)